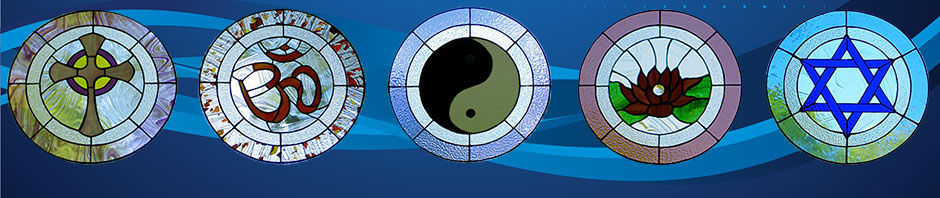中世から近代ヨーロッパにかけてトレパネーションという治療法が行われていました。
脳圧を下げるためにに頭蓋骨に穴を開けて硬膜(脳の髄膜の外層をなす強靭な膜)を剥き出しにします。
この治療法の恐ろしいところは頭蓋骨に開けた穴を塞がずに頭皮を縫い合わせてしまうことです。
頭痛や精神病の治療に効果があったと言われています。
さて当時はどのようにして頭蓋骨に穴を開けていたかですが、穴を開ける際に使用していた道具を紹介します。
上の画像の道具はOsteotomeと言います。
1830年代あたりにドイツ人のBernard Heineによって発明されました。
ノコギリやハンマーで頭蓋骨に穴を開けようとすると、周囲の細胞を傷つける恐れがありますがOsteotomeを用いればそのようなことを心配する必要はありませんでした。
尖端についているとがった金属を頭蓋骨に刺してこの道具を固定したら、上部にあるハンドルを回します。
するとチェーンソーのように刃のついたベルトが回転して頭蓋骨を切っていきます。
・・・これも麻酔なしで行ったのでしょうか?