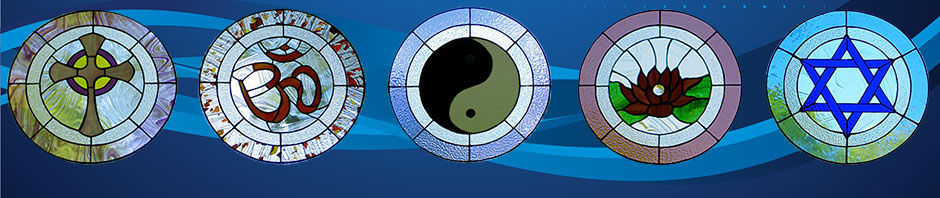今回は医療器具や治療法から離れて、本当にあったビックリするような手術について説明します。
当時27歳だったソビエトの医師、Leonid Rogozovwasは南極の基地に滞在していました。
彼はそこで腹部に鋭い痛みを感じたのです。
すぐさま虫垂炎であると診断を下したのですが、悪天候のため救援の飛行機はやって来ず、ただ見守ることしかできませんでした。
その間にも虫垂炎は悪化していき、このままでは命に関わる事態になりかねないと判断しました。
そこでLeonid Rogozovwasは自分で手術をすることにしたのです。
同じ基地にいた気象学者が手術の助手(後引筋を押さえる)をし、運転手はLeonid Rogozovwasが患部を見られるように鏡を固定し、他の科学者がLeonid Rogozovwasに手術道具を手渡しました。
手術は局部麻酔を使用して行われました。
手術中、Leonid Rogozovwasは一度意識を失いましたが、目を覚ましてから手術を続行し、無事に終えることが出来ました。
彼は2週間もしないうちに全快したそうです。